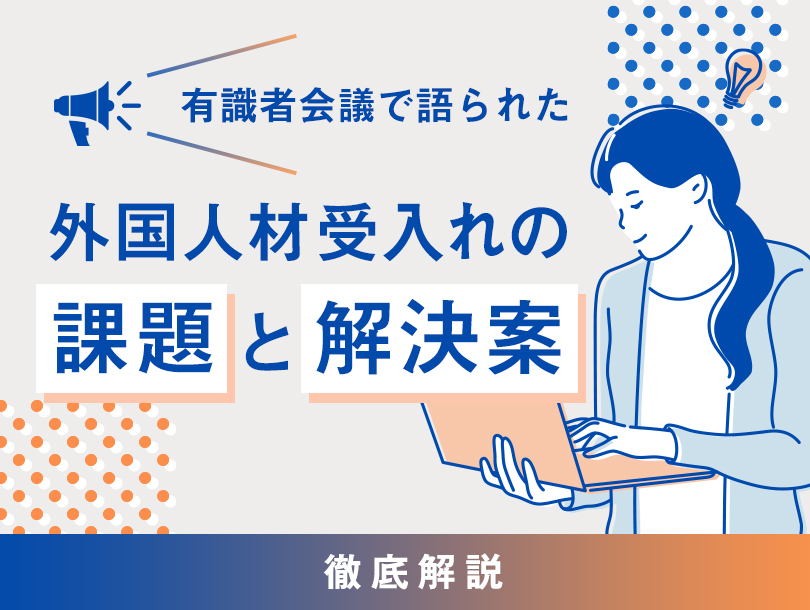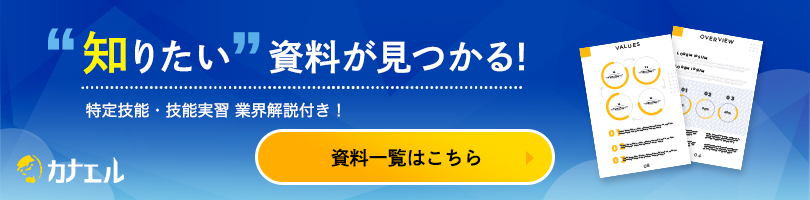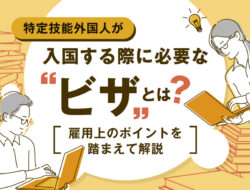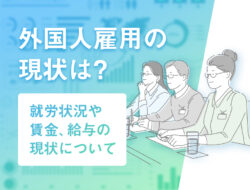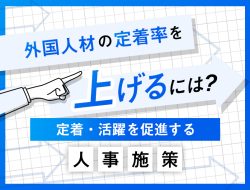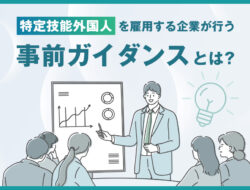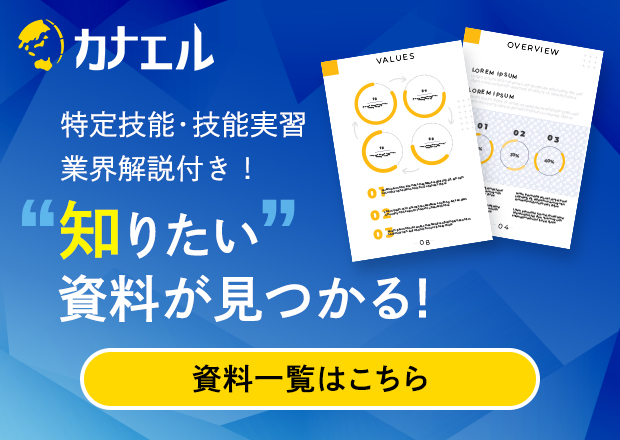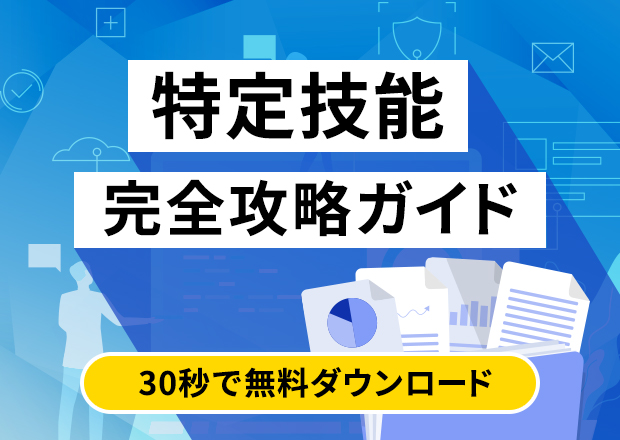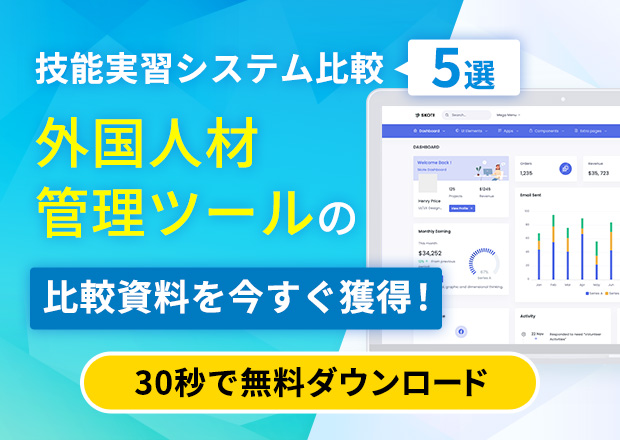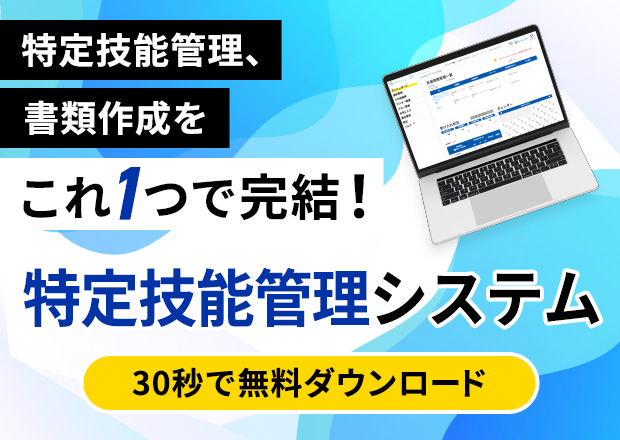これまで技能実習や特定技能といった制度の下、多くの外国人が日本で働いてきましたが、両制度にはさまざまな課題も存在しました。
国内での労働力不足が年々深刻化すると同時に、国際的に人材獲得競争が激化する今、日本は外国人材に選ばれる国になるためにもこうした課題を解決する必要があります。
従来の制度を見直し、具体的な方策を立てることを目的として2022年12月から2023年11月までの約1年間、「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」が開催されました。

目次
技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議
現在日本では多くの外国人労働者が働いていますが、彼らを取り巻く労働環境には常に多くの課題が潜んでいます。
以下では技能実習や特定技能として日本で働く外国人の現状と課題についての有識者会議の概要を解説します。
概要
現在日本国内には多くの外国人が来日し、技能実習や特定技能といった形で働いています。
少子高齢化に伴い今後国内で労働力が不足することが懸念される今、外国人材は日本経済を支える上で重要な存在となりつつあります。
しかし日本で働く外国人労働者を取り巻く環境にはさまざまな課題が存在するのも確かです。
技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議では、
- 日本で働く外国人労働者を取り巻く課題の解決
- 日本の経済力を維持すると同時に、年々国際的に激化している人材の獲得競争に勝つためにすでにある技能実習・特定技能制度の在り方についての見直しおよび新制度創設についての検討
が進められました。
構成員
有識者会議の構成員は以下の通りです。
座長
田中明彦(独立行政法人国際協力機構理事長)
座長代理
高橋進(株式会社日本総合研究所チェアマン・エメリタス)
構成員
市川正司(弁護士)
大下英和(日本商工会議所産業政策第二部長)
黒谷伸(一般社団法人全国農業会議所事務局長代理兼経営・人材対策部長)
是川夕(国立社会保障・人口問題研究所国際関係部長)
佐久間一浩(全国中小企業団体中央会事務局次長)
末松則子(鈴鹿市長)
鈴木直道(北海道知事)
武石恵美子(法政大学キャリアデザイン学部教授)
冨田さとこ(日本司法支援センター本部国際室長/弁護士)
冨高裕子(日本労働組合総連合会総合政策推進局総合政策推進局長)
樋口建史(元警視総監)
堀内保潔(一般社団法人日本経済団体連合会産業政策本部長)
山川隆一(明治大学法学部教授)
(50音順)
開催期間
2022年12月14日〜2023年11月24日(全16回)
技能実習概要
技能実習生は、「日本で働く外国人」として多くの人にとって非常に馴染みのある制度です。
目的
技能実習制度は日本での就労を通して技術・知識を培い、母国の発展に活かしてもらうことを目的とした制度です。
1993年に創設され、2017年には「外国人の技能実習の適正な実務及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」として改正し、運用されてきました。
国際貢献を目的とした制度であるため、本来は人手不足を補うために活用することは認められていません。
在留資格の概要
技能実習生の在留資格は1号・2号・3号に分けられ、最長5年の在留が認められています。また、実習修了後は母国に帰国することが前提となっており、永住権の取得には至りません。
技術修得のためには一箇所で一定期間就労することが望ましいとされていることから、技能実習生は原則として転職が認められていません。
特定技能概要
特定技能も技能実習に並び、「日本で働く外国人」として多くの人に認識されている制度です。
目的
特定技能制度は、人手不足解消を目的とした制度です。
国内で人材を確保することが特に難しいとされる産業分野において一定水準以上の日本語能力と技能・知識を持つ外国人材を受け入れることが可能です。
2019年から実際の運用が開始され、現在は16の産業分野で活用されています。
在留資格の概要
特定技能の在留資格は技能水準に応じて1号と2号に分類されます。取得により高い技能水準が求められる2号には在留期限がなく、永住権取得を目指すことが可能です。
また、2号を取得すると家族(配偶者と子のみ)の帯同も認められます。
その他にも要件を見たせば転職も可能であることや、1号であっても在留資格取得に際して一定水準以上の日本語能力を有することが求められる点が技能実習とは異なります。
日本で働く外国人材が抱える課題

外国人が日本での労働や生活に慣れるためには相応の時間やケアが必要になります。
言語や文化的背景が異なることが原因となり、労災に巻き込まれてしまう外国人も少なくありません。
外国人材に安心して働いてもらうためにも、従来の制度よりも日本語修得の機会を増やすなどの工夫が必要です。
また、外国人材を監理・支援・保護するため、監理団体や受入企業、ハローワーク、地方出入国在留管理局など関係機関の連携も強化する必要があります。
国際的にも理解が得られ外国人材に選ばれる国になる必要性
現在日本では少子高齢化の深刻化に伴い、さまざまな産業で労働力不足が叫ばれています。人手不足の問題を放置しておくと、日本経済全体が衰退しかねません。
一方で人手不足の課題を抱えているのは日本だけでなく、現在中国を始めとする各国で労働力確保のための外国人材の受入れが進められています。
人材の獲得競争が激化する中で国力を維持・発展させ続けるためにも、日本は給料だけでなくさまざまな点から外国人に選ばれる国になる必要があります。
現行制度を見直すにあたっての3つの視点

従来の技能実習・特定技能は外国人の雇用制度として日本国内で広く活用されてきましたが、さまざまな課題を抱えているのも事実です。
課題の中には国際社会からも批判されているものもあります。
日本は国際的にも理解が得られ、外国人材から選ばれる国になるためにも、現在抱える課題を解決しなければなりません。
有識者会議では以下の3つの視点を定めた上で、技能実習・特定技能など外国人労働者の置かれた現状と課題の洗い出しや、現行制度の見直しが進められました。
1.外国人の人権保護
言語や文化の壁がある外国人労働者は日本の職場で立場が弱くなりがちです。誰にも相談できないまま追い詰められてしまう人も少なくありません。
外国人労働者を取り巻く環境を改善するために、実態に即した制度の見直しや、監理団体の許可要件等の厳格化や、関係各機関の連携を強化する必要があります。
2.外国人のキャリアアップ
例えば技能実習から特定技能への移行ハードルが高いことは、受入企業にとって不都合であるだけでなく、日本における外国人労働者のキャリアアップを阻む要因となります。
外国人が日本でキャリアアップでき、活躍できる仕組みづくりが求められます。
3.安全安心・共生社会
日本人と外国人の両方が一緒に気持ちよく働ける労働環境を実現するためにも、外国人が日本語・技能が向上できる環境を整備するなど、外国人と日本人双方が安心できる社会作りが必要です。
4つの方向性
有識者会議では上記の3つの視点を踏まえた上で以下の4つの方向性に従い、現行制度の見直しが進められました。
- 技能実習制度を人材確保と人材育成を目的とする新たな制度とするなど、実態に即した見直しとすること
- 外国人材に我が国が選ばれるよう、技能・知識を段階的に向上させその結果を客観的に確認できる仕組みを設けることでキャリアパスを明確化し、新たな制度から特定技能制度への円滑な移行を図ること
- 人権保護の観点から、一定要件の下で本人意向の転籍を認めるとともに、監理団体等の要件厳格化や関係機関の役割の明確化等の措置を講じること
- 日本語能力を段階的に向上させる仕組みの構築や受入れ環境整備の取組により、共生社会の実現を目指すこと
最終報告書でまとめられた10の提言
技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議の最終報告書では以下の10の提言がまとめられました。
1.新たな制度及び特定技能制度の位置付けと両制度の関係性等
外国人に3年間の就労を通して特定技能1号水準の技能・知識を身につけてもらうことを目指した、人材確保と人材育成を目的とする新たな制度を創設することの必要性が提示されました。
また、特定技能制度は現行制度を維持したまま現在の日本経済社会に適応するものに改正すると同時に、現行の技能実習制度が持つ国際貢献の目的は発展的に解消されます。
2.新たな制度の受入れ対象分野や人材育成機能の在り方
新制度での受入れ産業分野は、技能実習制度での職種等をそのまま引き継ぐわけではなく、現行の特定技能制度での産業分野を元に人材育成に的した分野を設定すべきであるとの意見がまとめられました。
3.受入見込数の設定等の在り方
既存の特定技能制度と同様、新制度でも産業分野ごとに受入れ見込み数を設定し、それを受入れの上限数として運用する方針が提示されました。
受入れ見込み数や産業分野は経済情勢等の変化に応じて適切に変更されます。
4.新たな制度における転籍の在り方
現行の特定技能制度でも外国人労働者の転籍(転職)は認められています。しかし積極的にサポートする機関が存在しないなど事実上転籍不可能であることも多いのが現状です。
新制度では監理団体やハローワークなどによる転籍支援の実施など、外国人労働者でも転籍しやすい環境づくりが進められます。
5.監理・支援・保護の在り方
監理団体や労働基準監督署、出入国在留管理局など関係機関の連携を強化し、特定技能外国人に対する相談・援助体制を強化することの必要性や、監理団体運営の許可要件等の厳格化が求められました。
6.特定技能制度の適正化方策
新制度は3年間の日本での就労後、特定技能1号へと移行する前提の制度です。
そのため新制度は、3年間の就労期間で特定技能1号の在留資格取得が可能な水準まで日本語能力や技能を身につけることを目指すとされています。
7.国・自治体の役割
関係各機関が連携することで、不適正な受入れ・雇用を排除し、日本語教育機関による適正な日本語教育の実施が求められました。
さらに自治体は共生社会の実現等の観点から外国労働者が暮らしやすい地域の環境づくりの取り組みを推進します。
8.送出機関及び送出しの在り方
二国間取決め(MOC)により、送出機関の取締りを強化します。さらに来日後のミスマッチ等を防止するために、送出・受入れ機関双方の情報の透明性を促進すべきであるとの意見がまとめられました。
また、外国人労働者が来日するための費用を抑えるために、各機関に対する支払い手数料を抑え、外国人と受入れ機関が適切に分担する仕組みを導入します。
9.日本語能力の向上方策
外国人労働者の日本語能力向上のために、継続的な学習を提供すると同時に、優良受入れ機関の認定要件に日本語教育支援に取り組んでいるかどうかを盛り込むとされています。
10.その他(新たな制度に向けて)
政府は現行制度下でも人権侵害行為に対し、可能な対処を迅速に行うべきであるとされました。
また新制度への移行に際し、政府は移行期間を十分に確保するとともに事前広報を徹底し、現行制度の利用者・関係者に不当な不利益を生じさせないよう配慮する必要性も指摘されています。
新制度育成就労制度
技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議で出された提言を元に、従来の技能実習制度に代わり、育成就労制度が創設されることになりました。
新制度「育成就労」の目的
新制度育成就労では、人材の育成と確保が可能になります。3年間の就労ののち、特定技能1号の在留資格取得を前提とした制度です。
従来の技能実習制度は国際貢献を目的とした制度でしたが、制度の目的と実態の乖離が国内外から指摘されているなど、さまざまな課題を抱えていました。
育成就労は従来の制度が持つ課題を解決し、日本と日本で働きたい外国人の双方が利益を得られる制度として運用されます。
開始予定時期
2027年
具体的な変更点
育成就労としての3年間の就労を通して特定技能1号になることを目指した制度であるため、従来の技能実習に比べ企業はより長期的に人材を確保しやすくなります。
また、外国人材の人権を保護するために技能実習制度とは異なり外国人材は要件を満たせば転職が認められる、監理団体になるための許可要件が厳格化されるといった変更が加えられます。
まとめ
技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議では、従来の技能実習・特定技能制度の見直しが進められ、新制度「育成就労」の創設について議論が交わされました。
人材育成と人材確保を目的とした育成就労制度の創設に伴い、技能実習制度は廃止され、特定技能制度も改正されることになります。
今後受入企業及び関係機関は制度移行に伴い柔軟に対応できるよう、新制度について正しい知識を身につけましょう。