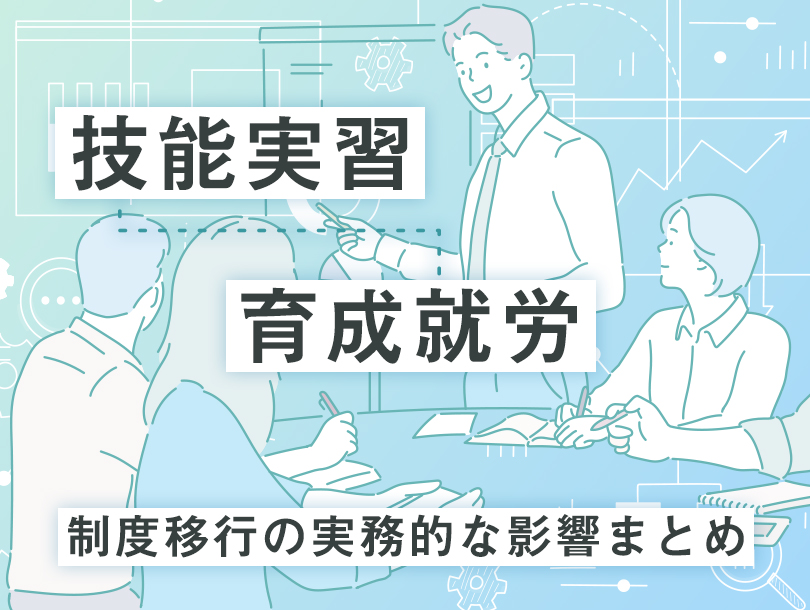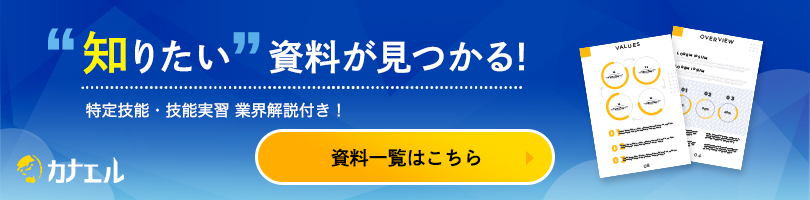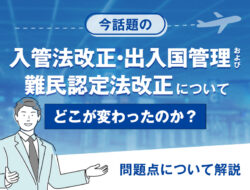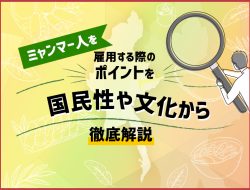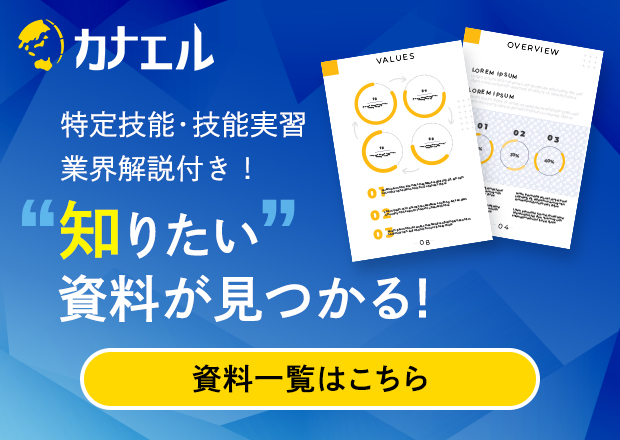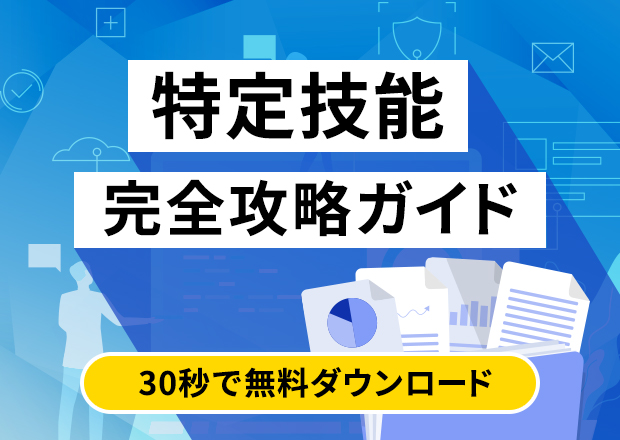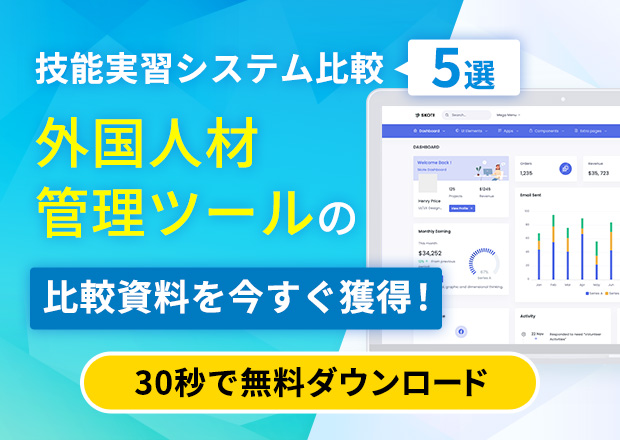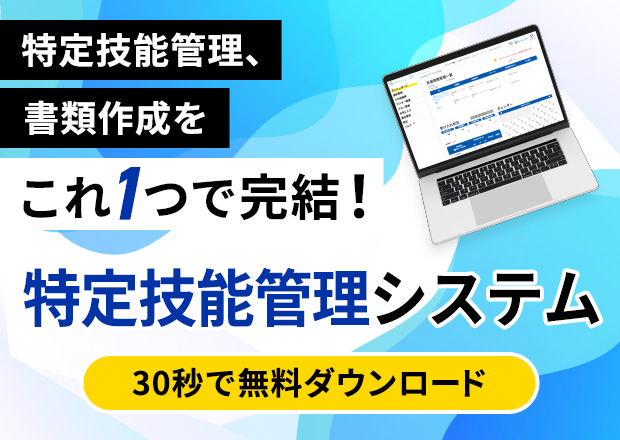目次
技能実習制度から育成就労制度へ移行する背景

まず育成就労制度に移行する背景から説明いたします。
主に以下の3点が理由としてあります。
目的と実態の乖離をなくすため
技能実習制度は、国際貢献のために主に発展途上国の人材への技能移転を目的としています。ですが実態は、外国人人材を労働力として活用しており、国際貢献という目的と、実態が異なっていることが長く指摘されていました。
この形骸化した建前をなくして、労働力として育成・日本社会への定着を図ることになります。
権利保護のため
技能実習生は労働者ではないため、転籍をすることなどは認められていませんでした。そのため厳しい労働環境でも耐えざるを得ません。また日本語力がまだまだつたない実習生も多いため、どうすることもできず、そのまま失踪してしまうという問題がありました。
労働者として認め、労働者として権利保護を行うべきだという声があったため、そちらの方針に舵を切ることになりました。
外国人人材に主体的に選んでもらうため
国際的な人材獲得競争が年々激化しています。
ですが日本の人手不足は加速する一方です。
そのため今後のことも考えて、外国人に主体的に選んでもらえる魅力的な制度を構築する必要があります。
主体的に選ばれる国となれば、人手不足に悩む産業を、長く人材の面で支えることができます。
法改正は技能実習制度をより発展させるものとなっています。
技能実習制度で指摘されていた①目的と実態の乖離、②外国人人材の人権問題を解決し、なおかつ主体的に選ばれる国となることをゴールとしています。
制度移行のスケジュール
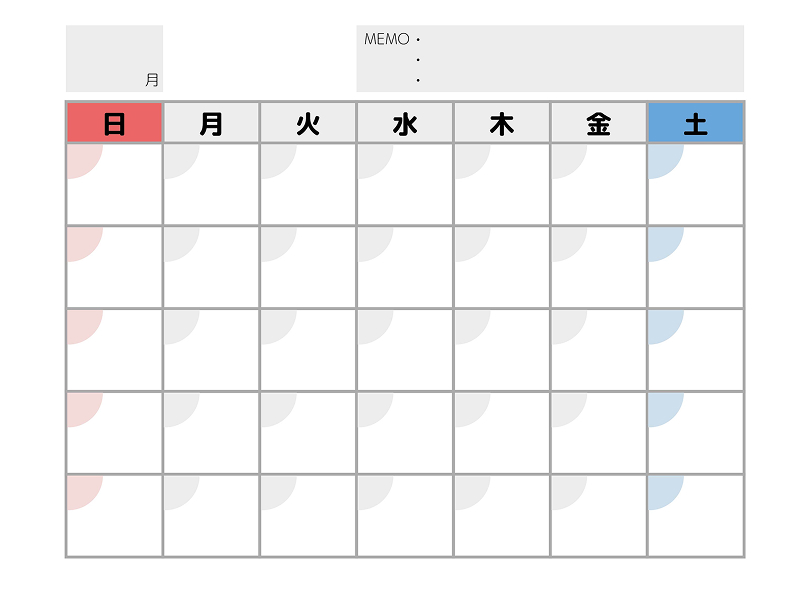
移行されるタイミングは改正法の公布日から3年以内の予定で、令和9年6月までには施行される予定となっています。ただ具体的な施行日はまだ未定なため、出入国在留管理庁のホームページでの続報を待つ必要があります。
また育成就労制度に関する主務省令も、公表時期はまだ未定となっています。
また、育成就労制度に関する主務省令も、公表時期がまだ未定となっています。
受け入れ企業が直面する実務変化
対象職種の変更と確認
育成就労制度の受入れ対象分野は、「育成就労産業分野」と呼ばれることとなりますが、この「育成就労産業分野」の具体的な職種はまだ決まっておらず、有識者や労使団体がメンバーとなる会議を経て決定します。
ただ技能実習の育成就労の受け入れ分野が全く同じになるとは限らないため、注意が必要となります。
育成就労から特定技能へのスムーズな移行を目指しているため、特定技能1号の職種をベースとして決定されるのではないかという見方があります。
技能実習と育成就労の対象となる職種の差異
こちらもまだ未定ですが、出入国在留管理庁の資料によれば、現行の技能実習制度の職種が、そのまま引き継がれることにはならない見込みです。
技能実習→育成就労への移行をスムーズにするという狙いが、今回の法改正にはあります。
そのため機械的には引き継がれずに、特定技能制度の特定産業分野に準ずる職種が、育成就労制度の受け入れ対象職種となると考えられています。
結局のところ、まだはっきりしたことは言えませんが、
・特定技能の業務区分と同じ職種が受け入れ対象となる
・育成の終了時(1年経過以上あと)には特定技能への移行が基本
となる見込みです。
そのため技能実習にはあった職種でも、特定技能に移行できない一部の職種については、受け入れ対象外になる可能性があります。
監理団体の役割変化

監理団体という名称から、監理支援機関という名称に変わる予定です。
名称は変わりますが、監理支援機関の役割は基本的には技能実習制度の監理団体と同じです。
主な役割として主務大臣の許可を受けることが必須ですが、そのうえで、受け入れ先企業と育成就労生のマッチング、育成就労外国人の支援や保護があります。
また育成就労実施者である受け入れ先企業への監理・指導も重要な責務となります。
監理支援機関は特に、受け入れ先企業への監理・指導、また育成就労外国人の支援・保護により力を入れることが期待されています。
また新たな役割として、以下の1つが課される予定です。
・転籍の支援
・役職員の関与の制限
・外部監査人の設置義務付け
・受け入れ期間数に応じた職員の配置義務付け
育成就労制度では、外国人本人の意志での転籍ができるようになります。
外国人本人から転籍希望の申し出があった場合には、その転籍の支援をすることも要件のひとつとなる予定です。この転籍の支援とは、具体的には、新たな受け入れ先企業など関係機関との連絡調整などとなる予定です。
育成就労の事務的な手続き
技能実習制度では、技能実習計画の認定手続きが必要でした。
育成就労でも、同じく、育成就労計画を作成し、認定手続きをすることが必須です。
この認定手続きの基本的な流れは、変わらない予定です。
ですが内容には変更点があります。
技能実習制度では、1号、2号、3号、それぞれの段階で、計画を作成して、認定するという流れでした。ですが育成就労制度では、基本的に3年間というスパンの中で、就労を通して技能を身に着けていきます。そのため初めから3年間の計画を作成して、認定を受けるというようになります。
現場で求められる具体的な準備
育成就労制度に今後は対応しなければなりません。
ですが、技能実習生をすぐ受け入れできなくなるわけではありません。
技能実習生の受け入れが、具体的にいつまでと説明することはできませんが、育成就労制度の施行日までに、技能実習計画の認定申請がされていて、また施行日から3か月以内に技能実習を始められる実習生までが対象です。
また育成就労制度がスタートしたときに、すでに技能実習を行っている外国人人材は、引き続き、技能実習を続けることができます。また技能実習1号であれば、技能実習2号に移行することも可能です。
ただ技能実習3号への移行に関しては一定の範囲のものに限るとされているため、その点には注意が必要です。
またあわせて特定技能制度の改正も行われる予定です。
こちらに関しては、支援の一部を委託している場合に対応が必要となります。
現在の技能実習制度では、登録支援機関の登録を受けていない機関に、支援の一部を委託できます。
受け入れ先企業で支援をすべて行うことが難しい場合があるための措置です。
ですが法改正により育成就労制度となると、支援業務の委託は、登録支援機関にしか委託できなくなります。
そのため受け入れ先企業が支援業務を行う、もしくは登録支援機関に支援を依頼する、どちらかの対応に舵を切らなければなりません。
移行期間の注意点と対応
最後に、注意点について説明します。
まず現在の技能実習制度では、企業単独型と団体監理型の2種類があります。
企業単独型は、受け入れ先企業が外国人人材を雇用して、受け入れ先企業が技能実習を行います。
研修から技能の実習のすべてを行うことが求められます。
一方で、団体監理型は、監理団体が海外で技能実習生を募集します。その後、受け入れ先企業で技能の実習を行いますが、監理団体が支援・サポートをしてくれるシステムです。
育成就労制度でも、この体制を踏襲する方針です。
ただし名称が変わり、「単独型育成就労」、「監理型育成就労」となります。
ですが注意点があります。
それは技能実習生を、外国にある子会社などから、研修目的で受け入れている場合です。
これはいままでは技能実習としての受け入れとなっていましたが、今後は育成就労ではなく、「企業内転勤2号」という在留資格での受け入れとなる予定です。
この「企業内転勤2号」は、新たに創設される予定の在留資格です。
つまり今まで通り技能実習生での受け入れができなくなります。
例外もあります。
外国にある子会社などからの受け入れの場合でも、3年間の就労を通して、人材育成を行う場合には、育成就労の考え方と同じであるため、育成就労制度で受け入れが可能です。
この場合はもちろん「監理型育成就労」ではなく「単独型育成就労」での受け入れとなります。
また外国の取引先企業から、企業単独型で技能実習生を受け入れることができましたが、これもできなくなります。ただし「単独型育成就労」では可能です。
まとめ

最後に今回の記事の概要をまとめます。
技能実習制度から育成就労制度へ移行する背景
出入国在留管理庁のWebページによると、以下の3点を理由としてあげています。
1.目的と実態の乖離をなくすため
国際貢献が本来の目的でしたが、実際は、外国人人材は労働力として活用されていました。
この形骸化した建前をなくして実態に即した内容に変更するべきだという考えから、法改正が行われたという背景があります。
2.権利保護のため
また労働者として認めて、労働者としての権利を保護するべきだという意見もあり、今回の法改正となりました。労働者として認めていく方針がほとんど決定しているため、新制度では本人意思での転籍などができるようになる予定です。
3.外国人人材に主体的に選んでもらうため
国際的な人材獲得競争が年々激化しているので、外国人が主体的に日本を選んでくれるように、魅力的な制度作りをするべきだという考えもありました。来日した外国人人材に、長い期間日本の産業を支えてほしいという考えから、制度変更の運びになりました。
技能実習制度→育成就労制度の主な変更点
目的
技能実習制度の目的は国際貢献でしたが、育成就労制度では、国際貢献ではなく人材確保を新たな目的としています。
転籍が可能
以前は受け入れ先企業の倒産などでしかできませんでした。
ですがパワハラなどを理由とした転籍も可能となると予想されています。
そして外国人本人の意思による転籍も可能となります。
育成就労制度の創設はいつ?
令和9年6月までには施行される予定となっています。
ただ具体的な施行日はまだ未定なため、出入国在留管理庁のホームページでの続報を待つ必要があります。
受け入れ企業が直面する実務変化
対象職種の変更と確認
ただ技能実習の育成就労の受け入れ分野が全く同じになるとは限らないため、注意が必要となります。育成就労から特定技能へのスムーズな移行を目指しているため、特定技能1号の職種をベースとして決定されるのではないかという見方があります。
技能実習の際にはあった職種が、育成就労ではなくなるという可能性も0ではありません。
監理団体の役割変化
監理団体という名称から、監理支援機関という名称に変わる予定です。
監理支援機関の役割は基本的には技能実習制度の監理団体と同じです。
また新たな役割として、以下の4つが課される予定です。
・転籍の支援
・役職員の関与の制限
・外部監査人の設置義務付け
・受け入れ期間数に応じた職員の配置義務付け
育成就労制度では、外国人本人の意志での転籍ができるようになります。
外国人本人から転籍希望の申し出があった場合には、支援をすることも要件のひとつとなる予定です。また転籍支援とは、外国人本人から転籍希望の申し出があった場合には、監理支援機関は関係機関との連絡調整などを行う予定です。