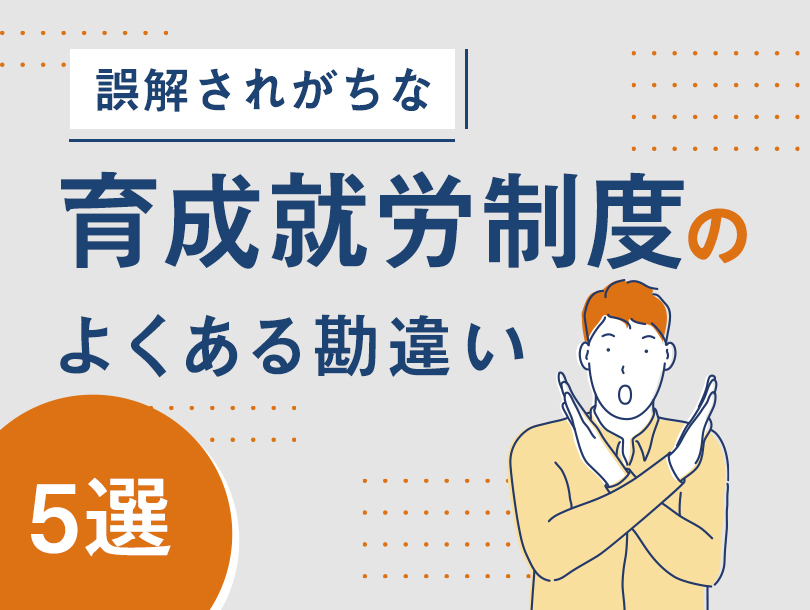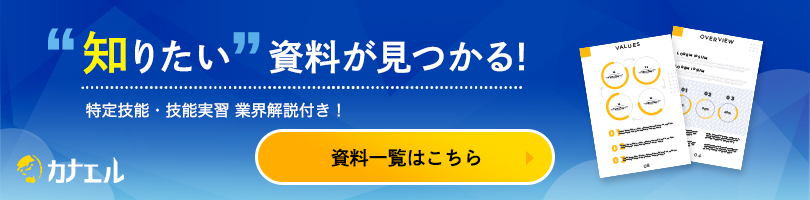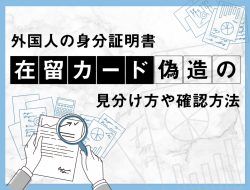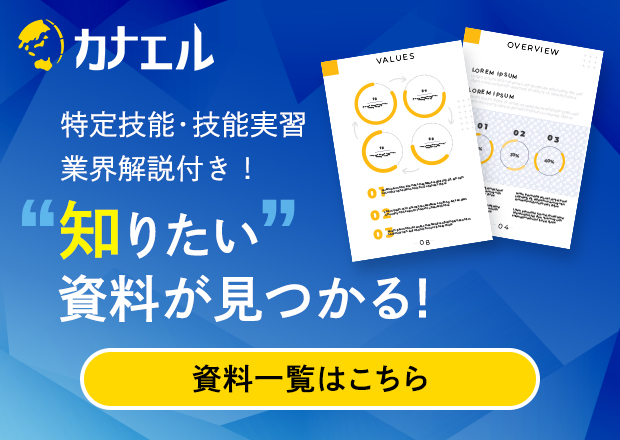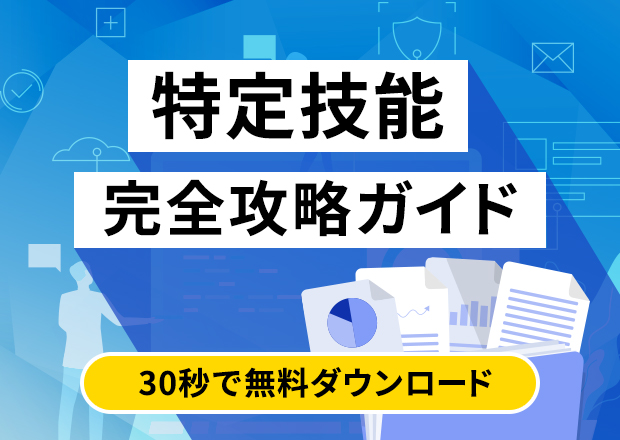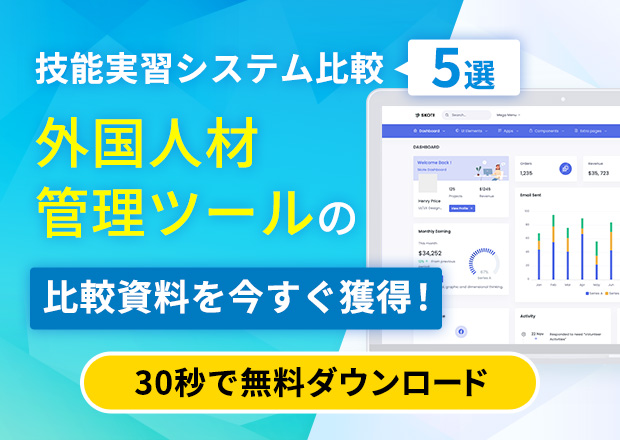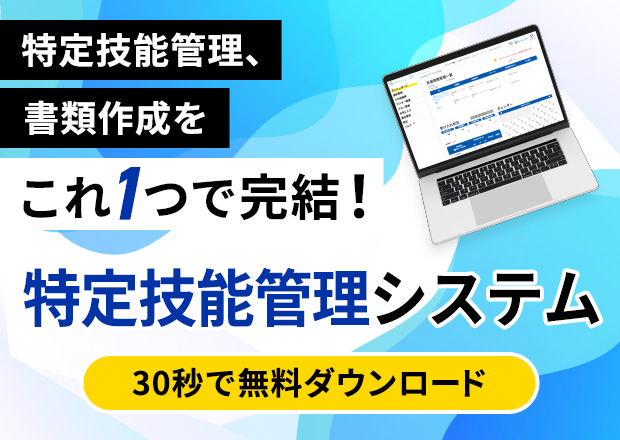「育成就労」制度は、外国人材の確保と育成を目的とした新制度です。
現行の技能実習制度に代わり、2027年に導入が予定されています。
労働力不足が深刻化する日本において、この新制度は日本の産業構造に良い影響を与えると考えられています。
しかし、その一方で、制度の全体像や詳細な変更点について、必ずしも正確に理解されているとは言えないのが現状です。たとえば「育成就労」は、「従来の技能実習制度の延長線上にある」「単に名称が変わるだけだ」、そう考えている方も少なくありません。
本記事では、そうした現状を踏まえ、多くの人が抱きがちな「育成就労」制度に関するよくある誤解や勘違いに焦点を当てて解説します。
目次
誤解1:「育成就労は、単なる技能実習の名称変更に過ぎない」
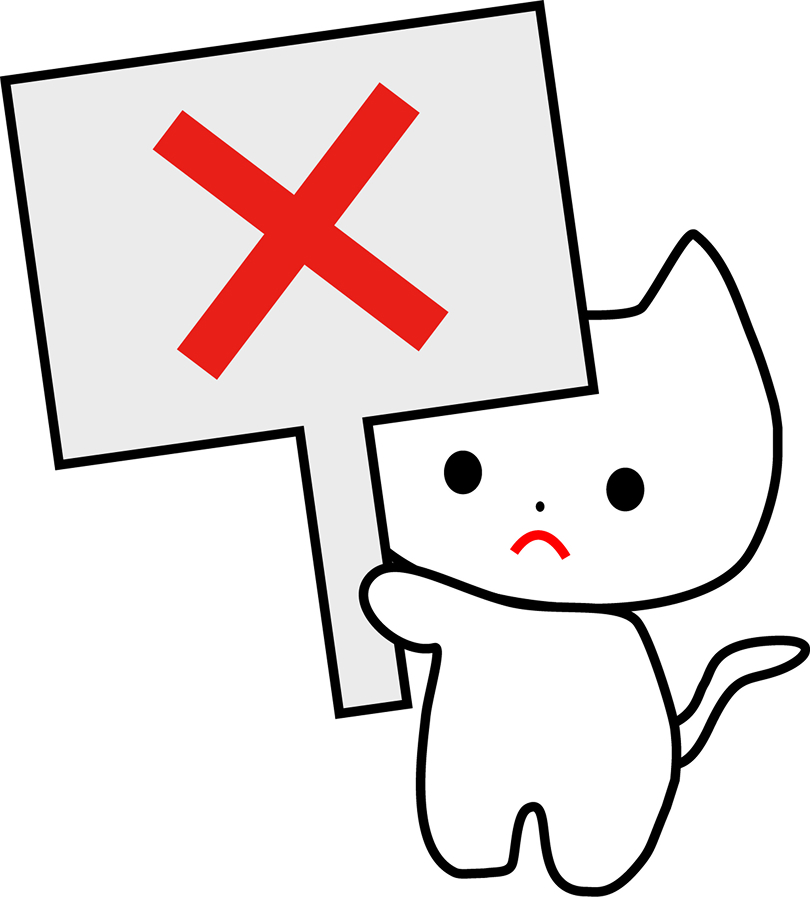
育成就労制度は技能実習制度の単なる名称変更ではなく、技能実習制度と目的や本質も大きく異なります。
形骸化した技能実習の建前
本来の技能実習制度の目的は、主に発展途上国の人材への「技術や知識の移転による国際貢献」でした。つまり技能実習制度の目的は、日本の先進的な技術や知識を、実習生に習得してもらい、その技術や知識を母国の産業発展に活かすことでした。
ですが実際には技能実習制度は、人手不足を補うための安価な労働力確保の手段として利用されていました。そのために以下のような問題点が指摘されています。
学んだことを、母国で生かすことができていない
本来の目的は技術や知識の移転でしたが、母国に帰っても、それを活かせる現場がなく、ただ日本で出稼ぎとして労働するだけになっていました。本来の目的の「技術や知識の移転」は完全にただの建前となっていました。
転職の制限
基本的には技能実習生は実習先の変更ができません。
そのため劣悪な労働環境に置かれても耐えるしかないというケースが多く、それに端を発する実習生の失踪も問題になっています。
上記のような問題から、国際社会から「奴隷労働」と批判を受けることすらありました。
育成就労制度の変更点
1.目的が変わった
上記のような問題点があったため、育成就労制度はそれらを解決するためにまず目的の面で大きく舵を切りました。
育成就労制度では、人材の確保・人材の育成が目的となります。
建前となっていた国際貢献を廃止して、明確に「人材確保」、そして外国人人材の育成を目的として打ち出しています。
また国際的な人材獲得競争が激化しているため、外国人に主体的に選んでもらう国になりたいという意図もあります。
2.転籍の条件緩和
技能実習制度では、基本的には、同じ企業で就労を続けなければなりませんでした。
(倒産などの場合のみ、転籍ができました)
そのため劣悪な労働環境であっても耐えるしかなく、失踪などの問題につながっているとの意見がありました。
ですが育成就労制度では、パワハラや暴力などの人権侵害を受けた場合には、基本的には転籍を認める方針です。また日本語力や、技能の水準が一定以上であるなどの条件を満たしていれば、本人の意思による転籍も認める方針です。
そのためただの名称変更ではなく、制度の目的や外国人人材の人権保護に関しても大きく変化しています。
誤解2:「育成就労は単純労働者の受け入れが目的」
こちらも誤解です。
育成就労制度には、人材確保の側面も確かにありますが同時に「育成」の側面もあります。
育成の側面
育成就労制度では技能実習制度が抱えていた課題を改善して、さらに技能と日本語能力を習得してキャリアアップできるように設計されています。
確かに育成就労制度では、日本の深刻な人手不足の分野、例えば介護や建設、農業や製造業などでの労働力確保を目的としています。
ですが一時的な労働力としてではなく、3年間の就労を通じて、特定技能1号レベルの技能および日本語能力を習得してもらい、その後スムーズに特定技能制度へ移行することを目指しています。
そのため一時的な単純労働者の受け入れではなく、外国人人材が日本でキャリアを形成して、より長く、安定的に就労できるような道筋を作ることを意図しています。
つまり育成就労制度は、特定技能制度へのスムーズな移行を目指した「人材育成」プログラムであるということもできるでしょう。
誤解3:「転籍が自由になり、企業は簡単に人材を失うリスクがある」
育成就労制度では、本人意思の転籍が可能になる予定です。
そのため企業側から見れば「せっかく育てた人材が他社へ流出するリスクが高まる」と感じるかもしれません。
しかし、この「転籍の自由」には一定の条件が設けられており、日本人と同じように、好きなときにいつでも簡単に転籍できるわけではありません。
下記のような条件があります。
同一の業務区分であること
同じ業務区分にしか転籍ができません。
全く異なる分野への転籍を認めない理由は、人材育成の制度のため、キャリアの継続性を重視しているためです。
業務に従事していた期間が所定の期間を超えていること
一定の期間、業務に従事していないと転籍はできないというルールが設けられる予定です。これも人材のキャリアの継続性を重視して、スムーズなスキルの向上をねらうためです。
技能と日本語能力が一定レベル以上であること
主に上記3つの要件を満たしていることが必須です。
受け入れ先企業は、費用・時間をかけて育成した人材がたとえば都市部に移るリスクを考えたり、来日費用などの初期費用の回収の点を不安に思ったりという面で懸念があるかと思います。
確かに技能実習制度に比べ、育成した人材の流出リスクは増加するかもしれません。
ですが技能実習制度では特別な場合以外では、転籍が認められず、劣悪な労働環境や人権侵害があっても、耐えるしかなく、その事実が外国人労働者の失踪という結果につながっています。転籍の自由を認めることで、外国人人材の人権侵害を防ぎ、日本全体が外国人人材が活躍しやすい環境を整えることができます。
そのため簡単に人材が流出するわけではなく、むしろ優秀な外国人人材が主体的に日本を選んでくれるようになるという側面があります。ですので長期的に見れば企業にもメリットがあります。
誤解4:「育成就労制度は外国人労働者の低賃金・劣悪な労働環境を助長する」

このような懸念がある理由は、技能実習制度のマイナス面のためです。
技能実習制度は「国際貢献」が目的でしたが、前述のように実態は人材確保の制度となっており、なおかつ劣悪な労働環境や低賃金を強いられたために失踪する実習生もいました。
そのため残念ながら、実習生を安価な労働力として考えている受け入れ先企業も、一部ありました。
ですが育成就労制度では、これらの技能実習制度の反省点が改善される予定です。
転籍が劣悪な労働環境を是正する
まず転籍が原則容認される予定です。
転籍が可能となると、劣悪な労働環境が是正されるのではないかと考えられています。
外国人人材は、労働環境が劣悪だったり、パワハラがあったりした場合には、別の受け入れ先企業に転籍ができるため、そのような受け入れ先はだんだんと淘汰されることが予想されます。
また条件として同じ業務区分であること、また原則1年以上の就労が必要などがありますが、それらの条件を満たせば自分の意志での転籍も可能になる予定です。
「特定技能」への移行も視野にいれている
また特定技能へスムーズに移行できるように設計される予定です。
外国人人材が自身のキャリアを見据えてキャリアアップし、より高い技能と日本語能力を習得することを、いままでより具体的にイメージできるようになっています。
従来の技能実習制度では、特定技能にそのまま移行できない職種があったため、一部職種ではキャリアアップが困難でした。
ですが育成就労制度では、将来的により良い賃金・待遇を得やすくなっているので、「外国人労働者の低賃金・劣悪な労働環境を助長する」ものではなく、「劣悪な環境から人材が流出する」システムであり、スキルアップして所得のアップを狙うことができる制度となっています。
期待される新制度
育成就労制度の設計思想は、転籍の自由を可能とすることで、外国人材の権利保護やキャリアアップを促して、長期的な人材の定着や、日本社会での活躍を目指していると言えます。
ただ重要なのは、令和9年度に実施予定の育成就労制度が、実効性を持って運用されるかどうかです。
また何よりも、受け入れ先企業の意識改革が伴わなければ、技能実習時代と同じく劣悪な労働環境で働く外国人人材が出てくる可能性があります。
技能実習制度の問題点を是正し、より良い労働環境を目指す方向にあるため、現時点では「誤解」と言えるでしょう。
誤解5:「育成就労制度は日本の労働市場を奪い、社会不安を招く」
これも誤解だと言ってよいでしょう。
ですが「社会不安を招く」という懸念は、異なる文化の人々が一緒に暮らす際には、どうしても生じてしまうのではないかと思います。
労働力の「代替」ではなく「補完」
まず育成就労制度で受け入れる外国人人材は、日本人労働者の代替ではなく、補完であるということを認識するべきです。
日本では少子高齢化が急速に進んでおり、なかでも介護や建設、農業、製造業などで深刻な人手不足に直面しています。
このままでは日本の多くの産業が立ち行かなくなります。
そのため「人手不足が深刻な分野」において、外国人労働者を受け入れることになりました。つまり日本人だけでは持続困難な産業・サービスを支えるための人材確保の制度です。
共生社会の推進
ほとんどの社会不安は、情報不足や偏見から生まれます。
そのため政府や自治体は、正確な情報を提供するためポータルサイトを始めたり、地域住民と外国人材との交流を促進するイベントの開催なども行っています。
外国人が増加すると、それがそのまま治安悪化につながるという懸念を持っている人も一部には存在しています。ですが統計的には外国人犯罪のみが特に増加しているという根拠はありません。
まとめ
誤解1:「育成就労は、単なる技能実習の名称変更に過ぎない」
→技能実習時代は目的が「国際貢献」でしたが、育成就労となり目的が「人材確保」、「人材の育成」となりました。
誤解2:「育成就労は単純労働者の受け入れが目的」
→技能実習と違い、育成就労では「育成」の側面が強く打ち出されました。
具体的には技能実習と違い、育成就労では3年間の就労のあと、スムーズに特定技能制度へ移行できる設計になる見込みです。
→そのため技能実習と違い、キャリアアップの道筋がより明確になっています。
誤解3:「転籍が自由になり、企業は簡単に人材を失うリスクがある」
→転籍の自由を認めること=外国人人材の人権侵害を防ぐという意図もあります。
→また日本人と同じような感覚で転籍ができるわけではなく、「業務に従事していた期間が所定の期間を超えていること」など、満たすべき条件があります。
誤解4:「育成就労制度は外国人労働者の低賃金・劣悪な労働環境を助長する」
→まず技能実習制度から、育成就労制度になることで、目的が人材確保と人材の育成へと変化します。
→また特定技能へスムーズにキャリアアップできるように設計される予定です。
そのためただの人材確保ではなく、育成と、長期的な日本の労働力としての定着を考えており、劣悪な環境であれば転籍もできるようになる見込みです。
誤解5:「育成就労制度は日本の労働市場を奪い、社会不安を招く」
→育成就労制度は、日本の労働力の「代替」ではなく「補完」です。
→介護や建設、農業、製造業など、特に人手不足が深刻な分野で、外国人労働者を受け入れることで、日本人だけでは継続が難しいサービスを支えるための制度です。
育成就労制度を正しく理解して、異なる文化圏の人々と、ともに歩んでいく意識が、ますます重要となっています。