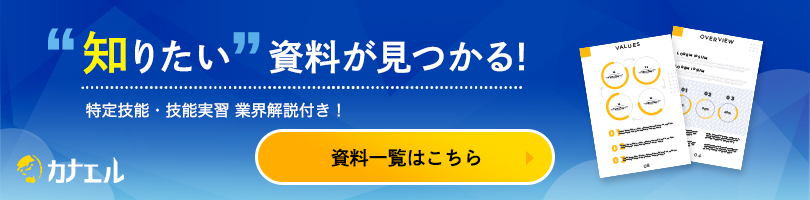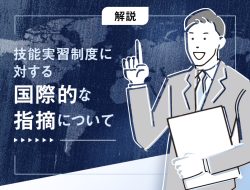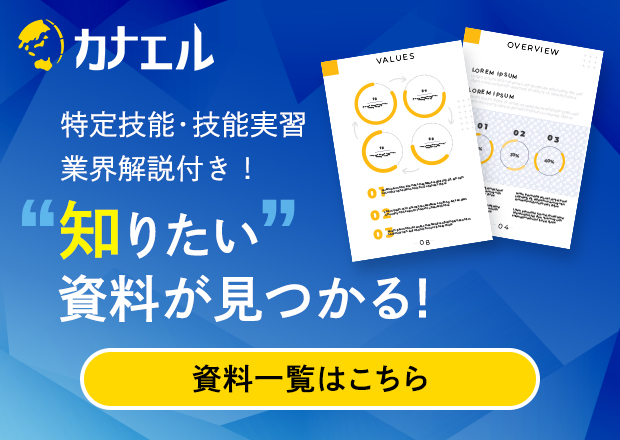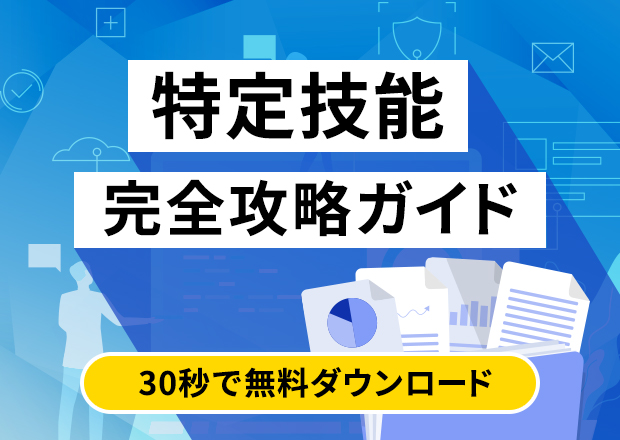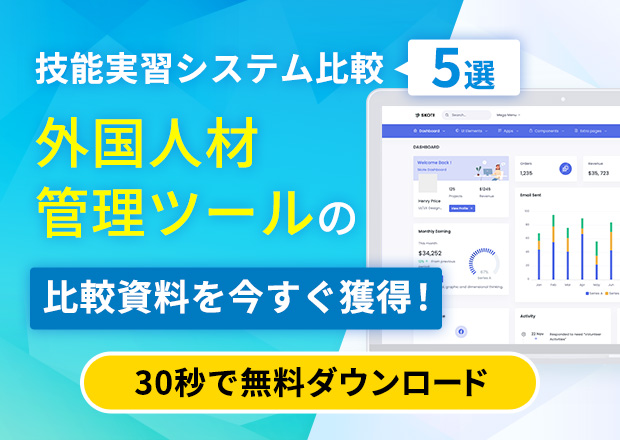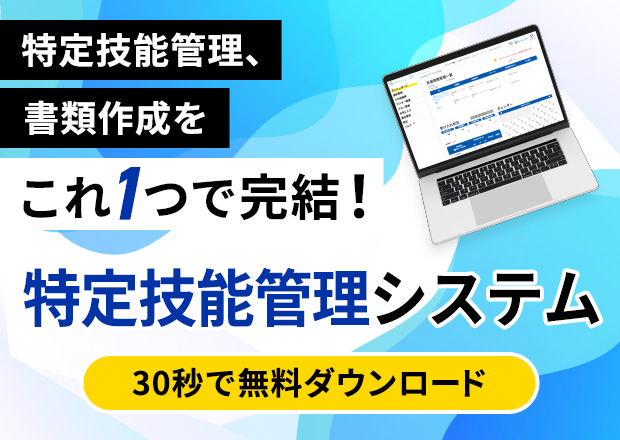日本では技能実習制度で長年、外国人人材を受け入れています。
ですが技能実習制度は「国際貢献」を建前としつつも、実質的には人手不足解消の手段となっており、残念ながら「人権侵害」などと国際社会からの批判を受けてもいます。それらを改善するために、技能実習から「育成就労制度」へと法改正されることが決まりました。
この法改正に伴い、OTIT(外国人技能実習機構)の役割も変わる予定です。
OTITは設立当初から、技能実習生の保護と監理を担う機関でした。技能実習制度から「育成就労制度」となり、外国人人材を受け入れる制度の目的・枠組みが見直されるため、そのOTITの実務における機能も変化していきます。
本稿ではOTITが抱えていた課題や、今後果たすべき役割について考察していきます。
目次
第1章:技能実習制度におけるOTITの役割と課題
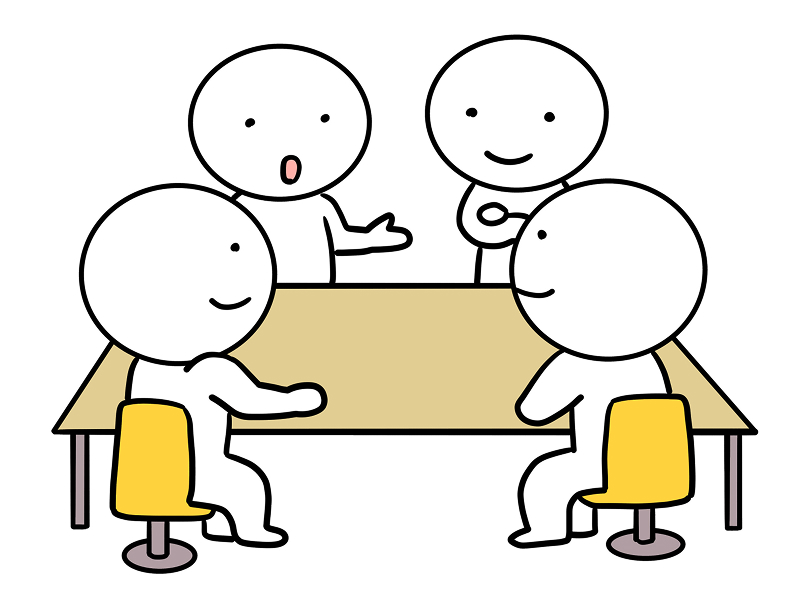
OTITは「Organization for Technical Intern Training」の略です。日本語では「外国人技能実習機構」といいます。外国人技能実習制度の適正な実施と、技能実習生の保護を目的としており、2017年4月1日に設立されました。
1. OTITの主な役割
まずはOTITの主な役割について、簡単に説明します。
OTITは技能実習法に基づいて技能実習生の保護などのため、技能実習制度が適正に実施されるように様々な役割をこなしています。
主な役割は以下になります。
認定業務
監理団体の許可
OTITは協同組合や商工会議所、職業訓練法人や公益社団法人などの監理団体に、審査を行ったあとに監理団体として認める旨の許可を与えています。審査では、その監理団体には問題なく受け入れ先企業を支援・監理する能力・体制があるかを確認しています。
このような審査と許可の認定業務が重要な役割の一つです。
技能実習計画の認定
そして企業が作成する「技能実習計画」の審査も行っています。
この「技能実習計画」には実習内容や期間、賃金、生活指導などについて記載があり、法律や基準に適合しているかを審査しています。
報告要求・実地調査の依頼
受け入れ先企業の技能実習計画を認定して、それで終わりではありません。
その後もしっかりチェックを行っています。
つまり受け入れ企業と監理団体に対して、技能実習計画通りに問題なく技能実習が実施されているかどうかの確認もしています。
その確認のため、受け入れ先企業や監理団体に報告要求、そして実地調査を依頼します。
依頼した実地調査などで、不適切な点が見つかった場合には、指導や勧告を行い、改善を促します。場合によっては技能実習計画の認定取り消しをする権限ももっているため、そのような処置を実施する場合もあります。
2. OTITへの批判
OTITは設立されて以来、外国人技能実習生たちの保護のため、監理団体を審査して問題なければ許可を与え、また技能実習計画のチェックもしてきました。
ここにチェックがはいることで、防ぐことができたトラブルはあったはずです。
ですが技能実習制度には課題は数多くあり、それらの課題の多くは解決がされませんでした。
この章では、OTITへの批判について見ていきます。
OTITの限界
一部、悪質な監理団体や受入れ先企業が存在していました。
具体的には賃金未払いやパワーハラスメント、過重労働も存在していました。
そういった受け入れ先企業に対して、OTITは認定取り消しなどの権限を行使することはもちろん可能です。
ですが受け入れ先企業は膨大なため、そのすべてに対して、監理を行き届かせることができておらず、賃金未払いなどの被害にある実習生がいました。
増える技能実習生の失踪者
OTIT設立後も、技能実習生の失踪者は高水準で推移し続けました。
出入国管理庁の資料によると、令和5年の技能実習生の失踪者数は、過去最大の9,753人です。技能実習生の失踪者問題は、変わらず日本の社会問題です。
技能実習者の失踪の理由として、ミスマッチ・労働環境の劣悪さがあげられると言われています。
雇用のミスマッチを防ぐために、たとえば実習生として来日が多いベトナムでは、ベトナム国内で仕事内容に関するリーフレットを作成して、技能実習の希望者に配って周知する活動などに取り組んではいます。
また特に失踪者が多い建設と農業の分野では、独自の失踪防止対策などをとっていますが、なかなか効果が上がってきていないという実情があります。
劣悪な労働環境から逃げ出す技能実習生もいることから「OTITの監督指導が十分に機能していない」という批判、またOTITではなくそもそも「制度の根本に問題がある」という批判もあります。
実習生の「保護」機能の不十分さ
OTITは技能実習SOSという相談窓口を用意してはいます。
技能実習SOSでは「殴られている」、または「強制的に帰国させられる」、「事業主か
らセクハラを受けている」などの事例で苦しんでいる場合、母国語でサポートをしてもらえます。
通話料無料のフリーダイヤルで、ベトナム語、中国語、インドネシア語、フィリピン語、英語、タイ語で相談することができます。
このような相談窓口が用意されており、また別途、「実習場所で法令違反が生じている」という場合に相談できる窓口も用意されています。
このような相談窓口を用意はしていますが、技能実習生が抱える賃金トラブルや暴力、セクハラなどを実際に解決する能力が、OTITには不足しているという批判があります。実際に、通報があった場合、OTITは状況をすぐ改善できないことも多々ありました。
また報復を恐れて、窓口があっても通報できないという声もありました。
監理団体への監督不足・癒着
さらにOTITが違法行為に加担して、訴訟されるという事件もありました。
ある事件ではOTITは「団結権侵害」について損害賠償請求をされていました。2024年10月31日に、OTITはその訴訟で、コミュニティユニオンと和解することができました。
ただこの事件では、OTITが自身の行為を不適切であると認めて損害賠償をしました。
この事件では退職強要・賃金未払い・パワーハラスメント・労災の被害にあったベトナム人女性3人がOTITに相談したところ、監督機関であるにもかかわらず、会社側の違法行為には技能実習生であるベトナム人女性3人にも非があるように彼女たちに伝えました。
「奴隷労働」との国際社会からの批判があったこともあり設立されたOTITでしたが、全く機能していないことが改めて浮き彫りとなりました。
第2章:「育成就労」制度の骨子とOTITへの期待
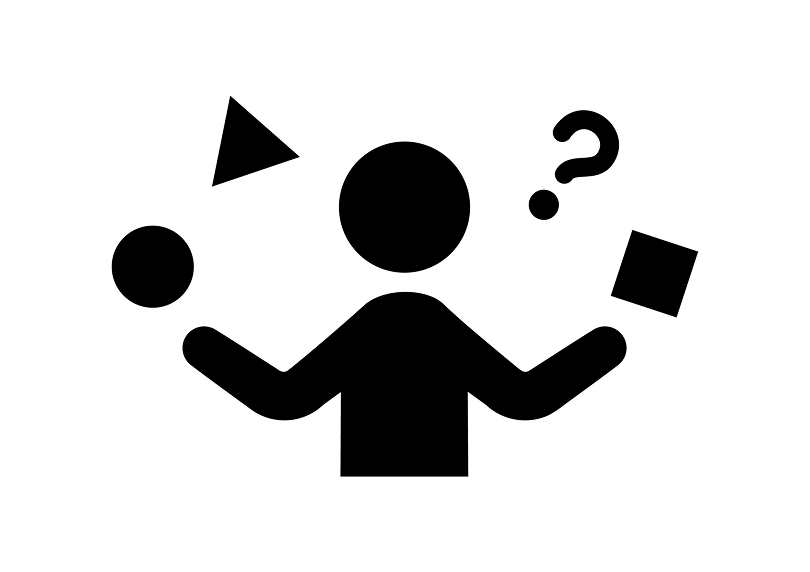
この章では「育成就労」制度の骨子、そして新しい制度の中でOTITに求められる役割について説明していきます。
育成就労制度の骨子
育成就労制度は技能実習制度が抱えている課題を克服して、外国人人材の権利保護と、日本社会への労働力としての長期的な定着を目的としています。
目的の変化
そのためにまず、技能実習制度の形骸化した目的を廃止する予定です。
技能実習制度では「国際貢献」が建前でした。
ですが「育成就労」制度では「人材確保」、そして「人材育成」を目的としています。
そのため新制度では日本の労働力不足を補完してキャリア形成を支援することが目的となっています。
転籍の原則容認
本人の意思による転籍が認められる方針です。
一定の要件(原則として同じ受け入れ先企業で1年以上の就労、また一定レベルの技能スキルなど)を満たせば、自分の意思で、受け入れ先企業を変更できます。
これは外国人人材の人権の保護に大きく関わってきます。
以前は劣悪な労働環境にいたり、不当な扱いを受けたりした場合には、耐えるしかありませんでした。OTITに相談しても即座の改善は難しい場合も多い実情がありました。
ですが転籍により、劣悪な労働環境から抜け出す手段を得られるようになる予定です。
特定技能へのキャリアップ
育成就労から特定技能へのキャリアアップが、スムーズにできる予定です。
ちなみに育成就労から特定技能2号へと移行ができれば、在留期間の制限が基本的にはなくなるため、より長い期間日本での労働が可能となります。
ですが現在の技能実習制度では「日本でもっと稼ぎたい」、「身につけた技能を活かしたい」という思いがあっても、特定技能へは移行ができない職種が多くあります。
スムーズに特定技能制度に移行できるよう設計することで、技能に習熟した外国人人材により長い期間働いてもらいやすくなりました。
OTITへの期待
育成就労制度への法改正に伴い、OTITの役割も大きく変化します。
たとえば転籍が容認される方針となるため、外国人人材の人権はより守られるようになりますが、OTITはパワハラなどの人権侵害や賃金未払いなどの、トラブルに対する通報窓口として変わらずしっかり責務を果たす必要があります。
違反行為をする受け入れ先企業に対しては、指導、状況によっては認定取り消しなどを断固として行い、悪質な受け入れ先企業は、育成就労制度の外国人材を、二度と受け入れられないような厳しい姿勢を示すことも不可欠です。
第3章:監理団体はどう変わるか
技能実習の監理団体は、技能実習が適切に運営されるように監理を行う団体のことです。
技能実習計画の作成指導をしたり、入国後講習を実施したりしていました。
また海外の「送り出し機関」と連絡を取って連携して、現地での求人活動や面接同行をしたりもしていました。
この監理団体は、育成就労制度では監理支援機関と名前を変えます。
監理支援機関と名称が変わっても現在の監理団体と同じく、受け入れ先企業に対する監理と指導、そして育成就労外国人の支援や保護などは変わらず行います。また国際的なマッチング業務もいままでと同様に行う予定です。
ですが技能実習時代と全く同じでは、同じ失敗をするリスクが高いままです。
そのため監理業務や育成就労外国人の保護などを、よりスムーズかつ適切に行えるように、許可の要件が見直されます。まず技能実習制度の監理団体は、育成就労制度へと法改正されてからは、監理支援機関として新たに許可を受けなければなりません。
肝心の許可の要件の詳細は、出入国在留管理庁のページによると、主に以下になります。
1.受入れ機関と密接な関係がある役職員は、監理への関わりが制限される
2.外部監査人の設置を義務づけられる
3.受入れ機関数に応じた職員の配置が義務づけられる
第4章:OTITの今後の課題と展望

技能実習制度から育成就労制度へ移行することに伴い、外国人技能実習機構であるOTITにも、今までと違った観点からの保護や支援が期待されています。
いまでも監視役としての役割が期待されています。
ですがそれに十二分に応えられているかというと、疑問が残るでしょう。
今後は受け入れ先企業や、監理支援機関の監視役としての役割も果たしながら、外国人人材の「保護」、そして「育成」をもれなくできる機関として、新たに生まれ変わることを期待されています。
なかでも新制度では「育成」の側面が目的にもあらわれています。
計画の認定業務や、監視役としての役割ももちろん重要です。
ですが「育成」の実効性確保も同時に、極めて重要となってきます。
外国人人材が技能や日本語能力を、安心して向上させる環境づくりが重要です。
そのために実習内容の質のチェックもそうですが、しっかりとした受け入れ先企業などの指導や監督が大切です。
また本人の意志での転籍が認められる方針です。
外国人材が不当な引き止めにあう可能性が、新たに出てきたと言うこともできるでしょう。
そういった新たに発生しうるリスクからの保護もおこないつつ、転籍先探しのサポートなども問題なく行える体制が重要となります。
いままでの役割はもちろん、新たな役割も果たしていく必要があります。
OTITは外国人人材の人権尊重と、人手不足で苦しむ産業の労働力確保を、同時に実現していかなければなりません。いままでの失敗や批判を活かして、信頼を回復していくことが必須です。この法改正を契機にその実現を推進できる機関に変貌ができれば、展望は明るいものになるでしょう。
まとめ
OTIT(外国人技能実習機構)には現状、様々な課題があります。
技能実習制度から育成就労制度に法改正をされるに伴い、OTITの役割も変化しますし、期待されることも変わります。
また転籍が容認される方針となりますが、そうなると、転籍をさせないための悪質な引き留めなどが行われる可能性もあります。いままでの失敗や批判を踏まえてしっかりと改善し、新たに発生するたとえば悪質な引き留めなどのリスクに毅然と対処する姿勢が求められます。
また違反行為をする受け入れ先企業に対しては、厳しい対応を徹底し、認定取り消しなどを場合によっては断固として行う姿勢も求められます。
OTITには反省を踏まえるだけではなく、新たな制度のなかで苦しむ外国人労働者を決して出さないという毅然と姿勢を見せることが求められています。