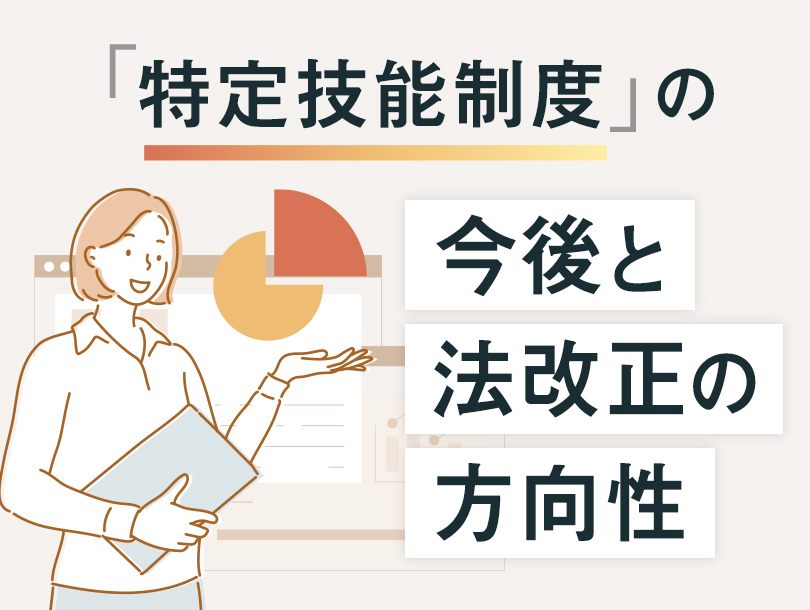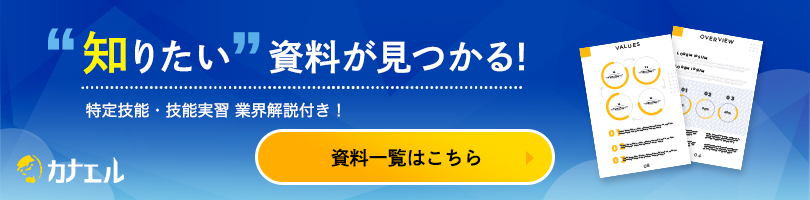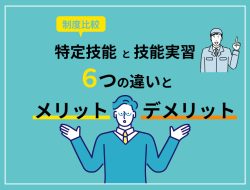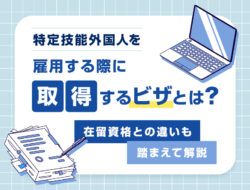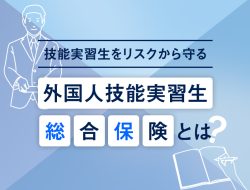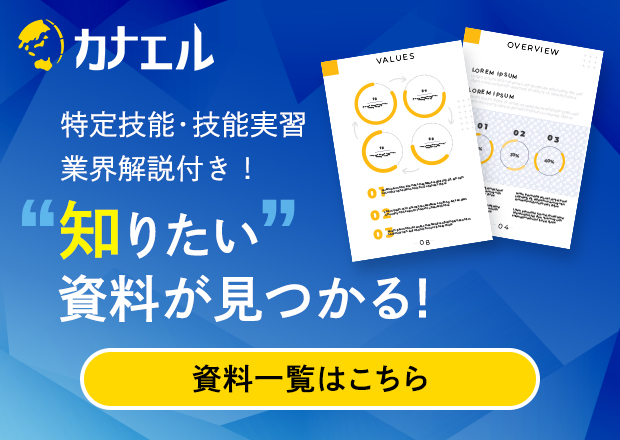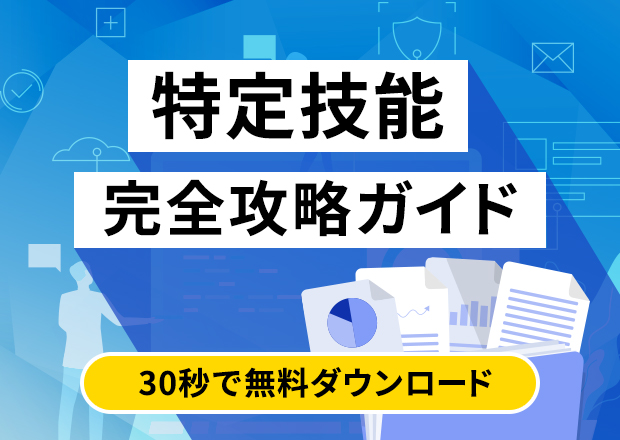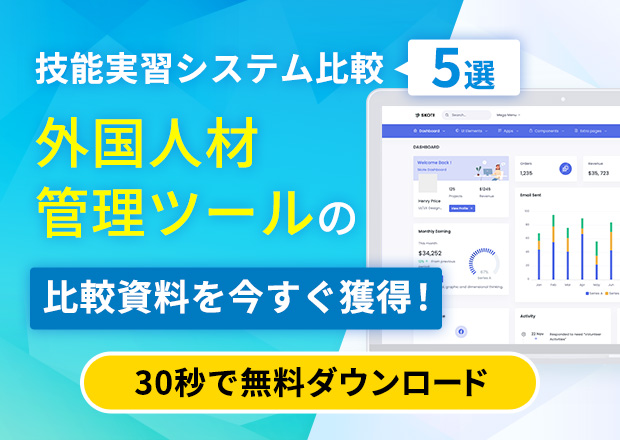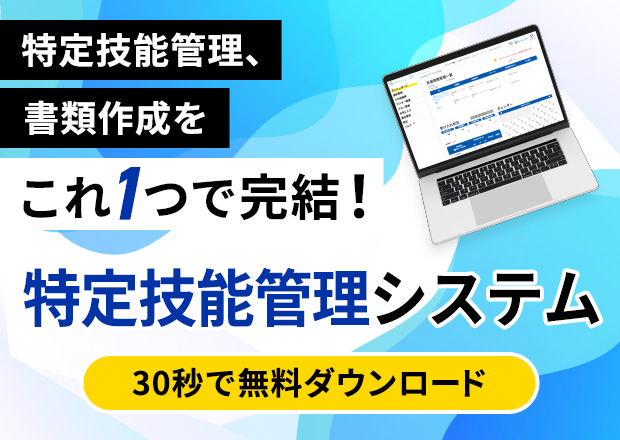特定技能制度の改正省令が令和7年4月1日から施行されました。
日本国内での外国人材の活用が進められるのに並行して、特定技能をはじめとする外国人の雇用制度も毎年のように見直されています。
この記事では令和7年の特定技能制度の改正ポイントと、令和9年に施行予定の新制度「育成就労」も踏まえた上での方向性について解説します。
目次
特定技能制度の概要

年々深刻化する労働力不足の問題を外国人材の活用によって解消することが特定技能制度の目的です。
現在日本国内のさまざまな産業で労働力不足が叫ばれており、少子高齢化に伴う労働力不足は産業に影響を与える可能性があるため、外国人材の活用が重要視されています。
こうした日本経済の崩壊リスクを回避するだけでなく、国内の産業をさらに発展させるために2019年に特定技能制度は創設されました。
現在は特に労働力不足が深刻とされている16の産業分野で活用が認められています。
改正省令が令和7年4月1日から施行
人手不足解消を目的としているため、特定技能制度は国内での労働力不足の深刻化に合わせて見直しが進められます。
直近では令和7年(2025年)4月1日に改正省令が施行されました。
今後も受入れ人数や対象産業分野、特定技能1号に対する支援内容、各種届出の頻度や内容などが見直されることが予想されます。
特定技能外国人の受入機関は改正があるたびに適切に対応するようにしましょう。
令和7年4月1日に施行された省令の具体的な改正点
以下では令和7年4月1日に施行された改正省令が、これまでのものと具体的にどのような点が異なるのかを解説します。
1.地域の共生施策との連携をより目指したものに
文化的背景や価値観が異なる外国人が日本で働き、生活する場合、地域との関係性も非常に重要になります。
今回の改正省令では、受入機関が特定技能1号の在留資格を持つ外国人に対し実施する支援計画は、地方公共団体が実施する共生社会実現のための施策を踏まえたものである必要性があることが加えられました。
受入機関は、支援計画を作成する際、1号特定技能外国人が実際に働く事業所の所在地及び居住地が属する市区町村が実施する共生社会の実現のための施策を確認しなければなりません。
2.各種届出の届出頻度・届出項目等の変更
受入機関には雇用する特定技能外国人について、定期あるいは随時所定の届出をする義務が課せられていますが、令和7年の改正省令では一部の届出について頻度や項目が変更されました。
変更・新設されたポイントは以下の通りです。
- 【変更】特定技能外国人の受入れ困難時の届出
- 【新設】特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の基準不適合に係る届出
- 【変更】特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況に関する届出
- 【新設】1号特定技能外国人支援計画の実施困難に係る届出
1.【変更】特定技能外国人の受入れ困難時の届出
今回の改正省令では、特定技能外国人の受入れ困難時の届出の届出事由について、
- 自己都合退職の申し出があった場合の取り扱い
- 1か月以上「特定技能」に基づく活動ができない場合の取り扱い
の2点が整理されました。
従来は雇用する特定技能外国人から自己都合による退職の申し出があった場合、「受入れ困難事由」として届出をする必要がありましたが、今後はその必要がなくなります。
ただし、自己都合退職の場合であっても「雇用契約終了の届出」は引き続き提出しなければなりません。
また、受入機関において1ヶ月以上特定技能に基づく活動ができない場合は、受入れ困難に係る届出を提出する必要があります。
なお、この届出は特定技能外国人が雇用後に1ヶ月以上活動ができない事情が生じた場合だけでなく、特定技能外国人が日本での活動許可を受けたあと、1ヶ月経過しても就労を開始できない場合についても提出しなければなりません。
2.【新設】特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の基準不適合に係る届出
従来は出入国又は労働関係法令に関する不正行為等(特定技能基準省令第2条第1項第4号リ)のみが届出の対象でしたが、今後は特定技能基準省令第2条第1項各号又は同条第2項各号の基準を満たさなくなった場合には届出なければなりません。
これによって「出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知ったときの届出」は廃止となり、今後は「特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の 基準不適合に係る届出」を提出することになります。
想定される届出事由としては、
- 税金や社会保険料等の滞納が発生した場合
- 特定技能外国人が従事する業務と同種の業務に従事していた日本人及びその他の在留資格で就労している外国人について、非自発的離職を発生させた場合
- 関係法律による刑罰を受けた場合
- 実習認定取り消しを受けた場合
- 出入国または労働関係法令に関する不正行為を行った場合
- 外国人に対する暴力行為、脅迫行為または監禁行為が発生した場合
- 外国人に対する手当や報酬の一部または全部を支払わない行為が発生した場合
などがあげられます。
3.【変更】特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況に関する届出
従来は受入れ・活動・支援実施状況について受入機関は四半期ごとに届出なければなりませんでしたが、今後は届出頻度が1年に1度に変更されます。
対象の4月1日から翌3月31日までの期間についての届出を、翌年の4月1日から5月31日までに提出しなければなりません。
さらに、従来は「特定技能外国人の受入れ・活動状況に関する届出書」と「支援実施状況に係る届出」が別々となっていましたが、今後はこの2つが統合され「特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況に関する届出書」として提出することになります。
支援計画の実施を登録支援機関に全て委託している場合は、受入機関が委託先の支援機関から支援の実施状況を取りまとめた上で「特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況に関する届出書」を提出する必要があります。
また、以下の条件を満たした受入機関である場合は、定期届出における一部を除いた添付書類の提出を省略することが認められます。
- 届出時点で基準に適合していることを誓約していること
- 過去3年間に指導又は勧告、または改善命令の処分を受けていないこと
- オンライン申請及び電子届出を活用することを誓約していること
- 適正な受入れを行うことが見込まれる受入れ機関であること
4.【新設】1号特定技能外国人支援計画の実施困難に係る届出
今回の改正によって、1号特定技能外国人に対する支援計画について、実施困難となる事由が生じた場合、当該認知の日から14日以内に「1号特定技能外国人支援計画の実施困難に係る届出」を提出しなければならないことになりました。
想定される支援の実施困難事由としては、
- 1号特定技能外国人支援計画に記載された支援が実施することができなかった場合
- 1号特定技能外国人との定期的な面談や相談等の支援を通じて本人の職業生活上、日常生活上、社会生活上の問題を把握し、自社でその問題を解決することが困難であり、行政機関等他の機関に相談を行うなどした場合(非自発的離職のため、ハローワークに相談をするなど転職支援を実施した場合も含む)
などがあげられます。
3.登録拒否事由
今回の省令改正によって、登録支援機関の登録拒否事由として、
- 1号特定技能外国人支援計画に基 づく支援に関し、出入国又は労働に関する法令違反や特定技能基準省令の基準不適合 等の事実を隠蔽する目的で特定技能外国人の意思表示等を妨げる行為又は必要な記録 等を作成しない行為
- 特定技能所属機関から全部委託を受けた支援の実施について、別の機関に再委託する行為又は再委託を受ける行為
- 1号特定技能外国人支援に関し、特定技能所属機関が基準不適合となった事実を隠蔽する目的で地方出入国在留管理局に必要な報告をしない行為又は虚偽の報告を行う行為
が追加されました。
4.登録支援機関の支援の実施状況等に関する届出・報告
受入機関から支援業務を受託する登録支援機関は、1年に1度、受託相手の受入機関を経由して支援実施状況を提出し、届け出なければなりません。
これは受入機関が支援業務を登録支援機関に委託する場合の話であり、先述の受入機関についての「特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況に関する届出」を実際に支援を実施する機関が作成するということになります。
法改正を受けて受入機関がとるべき対応
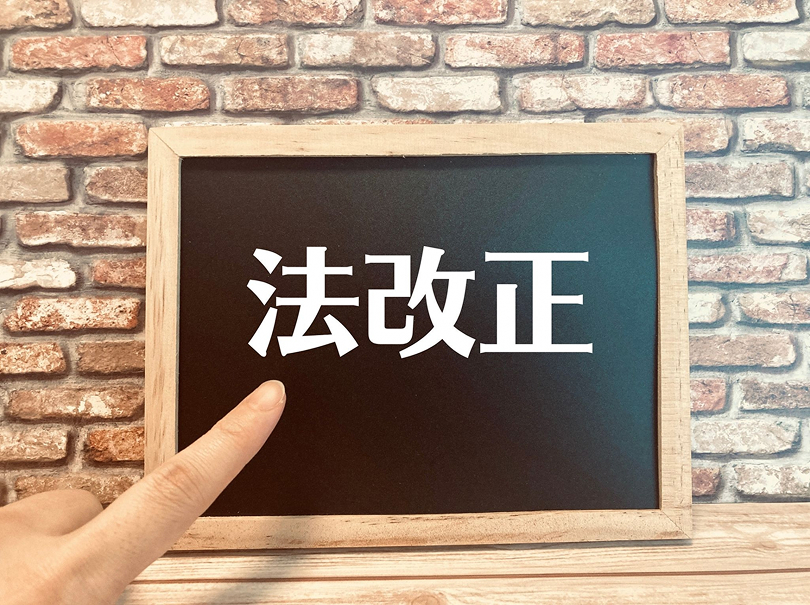
今回の法改正によって、受入機関がとるべき対応にも具体的な変更点が生じました。
自治体との連携強化
今回の省令改正で、受入機関が特定技能1号外国人に対し作成・実施する支援計画は、地方公共団体が実施する共生社会実現のための施策を踏まえたものでなければならないことが加えられました。
そのため、今後受入機関は外国人材の居住地および事業所の所在地が属する自治体が作成した施策を把握し、連携体制を強化しなければなりません。
必要な場合は現行の支援計画を見直し、自治体が作成した共生社会実現のための施策を踏まえたものに変更しましょう。
各種届出の内容とタイミングの再確認
今回の省令改正によって各種届出の内容と提出のタイミングが変更になったものも存在します。
届出を怠ると罰則の対象となる可能性があるため、各種届出の内容とタイミングの再確認をしましょう。
※対象年4/1から翌3/31までの届出を翌4/1〜5/31に提出必要
※定期届出の初回提出は2026年4月以降
法改正に至った経緯
今回の特定技能制度関連の法改正は、日本国内だけでなく世界の労働市場の現状を受け、実施されました。
従来の技能実習制度が抱えていた課題
長年「日本で働く外国人」として馴染みのある技能実習制度は、人材育成による途上国支援を目的として創設された制度でした。人手不足解消を目的として活用することは本来認められていません。
しかし実際には人手不足解消を目的として活用されることが多く、制度の目的と実態が乖離していると国内外から指摘されてきました。
また、技能実習制度は実習生である外国人の転職が認められていないなど、人権保護の面においても課題を抱えています。
さらに技能実習生から特定技能1号への在留資格移行ハードルが高く、外国人材の受入機関および日本で長く働きたい外国人双方にとって不便な側面もありました。
年々深刻化する労働力不足
少子高齢化に伴い、現在日本では、ざまざまな産業分野で年々労働力不足が深刻化しています。国内の産業や経済を維持・発展させるためには、外国人材の力が必要があります。
しかし異なる価値観・文化的背景を持つ外国人を雇用する際には、さまざまな配慮や工夫が求められます。
外国人材に健全な労働生活を送ってもらうだけでなく、雇用する側も安心できる仕組みをつくるために、特定技能制度を始めとする外国人の雇用制度の見直しは毎年進められています。
外国人材から選ばれる国になる必要性
国内で不足しがちな労働力を外国人材によって補おうとしている国は、日本だけではありません。現在先進国を中心に、多くの国が少子高齢化による労働力不足の課題を抱えており、人材の獲得競争は年々激化しています。
今後も経済・産業を維持発展し続けるためにも、労働環境の整備や、外国人にとって暮らしやすい環境づくりを進めることによって、外国人材からより選ばれる国になる努力が求められます。
新制度「育成就労」との関係

特定技能制度および外国人の雇用制度の見直し・改正にあわせ、新制度「育成就労」が創設されます。
育成就労制度はいつ始まる?
育成就労制度を含む改正法は2024年6月に公布され、公布日から3年以内に施行されること(=遅くとも2027年6月まで)とされています。ただし、具体的な施行日は未定です。
育成就労は特定技能1号取得を目指した在留資格
育成就労は日本での3年間の就労を通し、特定技能1号へと在留資格を移行させることを目指す在留資格です。
従来外国人の雇用制度として活用されてきた技能実習制度は、特定技能1号への在留資格移行ハードルが高いといった課題を抱えていました。
育成就労制度は原則として特定技能1号に準したものを対象産業分野とするなどの改善が加えられたものであるため、在留資格の移行が容易になります。
より長期的な人材確保が可能になる
技能実習制度とは異なり、育成就労は人材確保を目的として創設された制度です。そのため、受入企業はより長期的な人材確保が可能になります。
ただし、育成就労では外国人材の一定条件を満たした上での転籍が認められています。
都市部に人材が集中しない、転籍前の受入機関が負担した初期費用について正当な補填が受けられるといった配慮はされるものの、外国人材にとって働きやすい職場作りの努力は今後も必要です。
技能実習制度は廃止に
育成就労制度の施行により技能実習制度は発展的解消へ移行し、施行後は経過措置により併存期間が設けられます。
それまで技能実習制度を活用してきた受入機関が外国人材を活用し続けるためには、育成就労か特定技能に切り替える必要があります。
まとめ
今後日本国内での外国人材の活用が進められるにつれて、特定技能制度も見直しが進められることが予想されます。
法改正に則った対応ができるよう、最新の情報は常にチェックするよう心がけましょう。